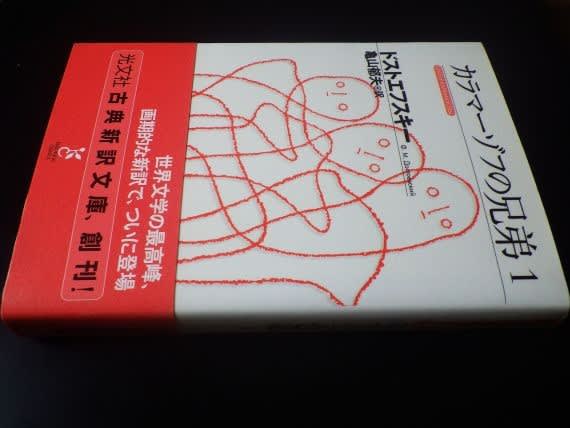『カラマーゾフの兄弟』読了計画の第9回は、(これまでの記事はコチラから)
第1部、第3編「女好きな男ども」の、

第6節、第7節、第8節。
「スメルジャコフ」(第6節)
「論争」(第7節)
「コニャックを飲みながら」(第8節)
の三つの節を読みたいと思う。

第1部、第3編、第6節「スメルジャコフ」
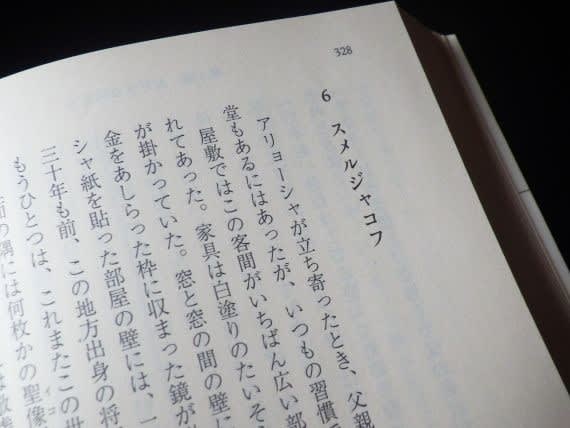
【要約】
アリョーシャが立ち寄ったとき、父親はまだ食卓についていた。フョードルは、毎晩ひどく夜更かしし、床に就くのは大体午前3時から4時と決まっていた。大抵は下男にスメルジャコフが一緒に部屋に居残るならわしだった。フョードルは、アリョーシャに酒を勧めてきたが、アリョーシャはコーヒーを頼んだ。フョードルは言った。「じつはおまえが喜びそうな話があるんだ。うちのバラムのロバが急に口をききだしたんだよ」。バラムのロバというのは、下男のスメルジャコフのことで、24、5歳という若さながら、おそろしく人づきあいが悪く無口な男だった。傲慢といってもよい性格で、すべての人を見下しているようなところがあった。子どもの頃、子猫を縛り首にし、その後お葬式の真似事をするために、彼は僧衣のかわりにシーツを纏い、子猫の亡骸を見下ろしながら歌ったり、香炉の代わりに何かを振り回したりした。あるとき、その現場を(育ての親ともいうべき)グリゴーリーに見つかり、鞭で大目玉を食らい、「おまえは人間じゃない、湿気た風呂場から沸きでたつんけなやつ、それがおまえなんだよ」と言われた。スメルジャコフが12歳の頃にグリゴーリーが聖書の話を教えていたときに、スメルジャコフが笑い出したので、「その笑いは何だ?」とグリゴーリーが言うと、屁理屈を言ってグリゴーリーをあざけるように見たので、グリゴーリーはスメルジャコフにびんたを一発見舞った。そうした矢先、スメルジャコフの身に初めて(その後も長く彼の一生につきまとう)癲癇(てんかん)の症状が現れたのだった。スメルジャコフが15歳になった頃、潔癖症の症状も現れ、どんな食べ物も顕微鏡を覗くようにしげしげと見るようになったのを見て、フョードルは彼を料理人にすることに決め、モスクワに修行に出した。数年後、戻って来たスメルジャコフは、異様なくらい老け込み、皺が増え、顔も黄ばみ、去勢派宗徒みたいな感じになっていた。精神面では以前と変わらず、人嫌いで無口だった。ただ料理人としての腕は申し分なかった。
この小説の語り部は、スメルジャコフを、クラムスコイの絵「瞑想する人」に例える。
画家のクラムスコイに『瞑想する人』という素晴らしい絵がある。冬の森が描かれ、その森の道で、このうえなく深い孤独にさまよいこんだ百姓が、ぼろぼろの外套にわらじというなりでひとり立ったままもの思いにふけっているのだが、彼はけっして考えているのではなく、何かを「瞑想している」のである。もしも彼の背中をとんと突きでもしたら、彼はぎくりと身をふるわせ、まるで眠りから覚めたように相手の顔をみるだろうが、そのじつ何も理解していない。
じっさい、すぐにわれに返るが、立ったまま何を考えていたのかと問われてもおそらく何も思い出せないにちがいない。しかしそのかわり、瞑想中の自分が抱いていた印象は、おそらく心のなかに深くしまいこんでいるのだ。彼にとってはこの印象こそが大事なのであり、彼はおそらくそれらをこっそりと自分でも意識しないままに蓄えているのである。ただしそれがなんのためであり、なぜかということもむろんわかっていない。多くの年月にわたってこれらの印象を溜め込んだあげく、ふいに彼はすべてを捨てて放浪と修行のためにエルサレムに旅立ったり、もしかすると故郷の村をとつぜん焼き払ったり、ことによるとその二つを同時に起こしたりするのかもしれない。民衆のなかにはかなりの数の瞑想者がいる。
思えばスメルジャコフもまた、おそらくはそういう瞑想者のひとりであり、自分でもなぜかはほとんど分からず、おそらくはむさぼるようにして自分の印象を溜めこんでいたにちがいない。(第1巻339~340頁)

第1部、第3編、第7節「論争」
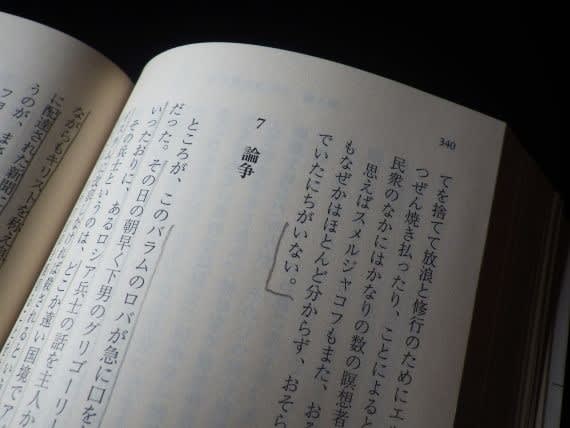
【要約】
バラムのロバが急に口をききだした。その日の朝早く、下男のグリゴーリーは買い出しに行った折、あるロシア兵士の話を聞いてきた。その兵士は、どこか遠い国境でアジア人の捕虜になり、キリスト教を捨てイスラムに改宗しなければ殺されるという状況下、自分の信仰を裏切れず、受難を受け入れ、生き皮をはがれながらもキリストを称え息絶えたというのだ。その英雄的な美談は、その日の新聞にも載っていた。それを聞いたフョードルは、「そういう兵士はすぐに聖人として祀り、剝がされた皮はどこかの修道院に送るべきだ。そうすりゃ人がわんさか押しかけて、賽銭も集まるしな」と、いつもの癖から罰当たりな物言いをした。すると、戸口に立っていたスメルジャコフがにやりと笑った。その薄笑いに気づいたフョードルは、「なんだい、それは?」と訊ねた。するとスメルジャコフが突然大声で話し出したのだ。「もしこの兵隊さんの行いが大層立派なものだとしても、こうした不慮の出来事でキリストの名や自分の洗礼を斥けることになったからといって、何の罪にも当たらないと思うんですよ。それで命が助かれば、その先いろいろと善行を積むことができますし、何年もかけて自分の臆病をあがなうことができますからね」。フョードルが、「どうしてそれが罪にならない? でたらめ言うな。そんなことを言ってると、おまえこそ地獄に突き落され羊肉(マトン)みたいにじゅうじゅう焼かれとまうぞ」と言ったとき、アリョーシャが入ってきた。「おまえにうってつけの話だ」と言って、話の続きを聞かせるためにアリョーシャを座らせた。スメルジャコフは言った。「かりにぼくがキリスト教の迫害者の捕虜になり、神の名を呪い、神聖な洗礼を拒否するように求めてきたら、ぼくはそれを完全に自分の理性で決めることができるんです。わたしはキリスト教徒ではありません……と言おうと思った瞬間、私は神様の最高の裁きによって破門者にされ、追放され、洗礼も解かれてしまい、何の責任もなくなってしまう。ぼくがすでにキリスト教徒でないとしたら、あの世に行ってから、ぼくは、キリストを捨てたことに対し、いったいどういうやり口で、どういう正義にのっとって、キリスト教徒と同じ責任を問われなくてはならないのでしょう。だってぼくはもうキリスト教徒としての資格を奪われているんですからね。迫害者たちに一言も口をきかないうちに、心のなかでそう思ったというだけの理由で……。頭のなかでそう思っただけで、洗礼は無にされ、ぼくはキリスト教徒じゃないのだから、キリストを捨てるわけもないんです。だって捨てるものが何もないんですから」。グリゴーリーは呆気にとられ、フョードルは甲高い声で笑った後、スメルジャコフを「イエズス会士」呼ばわりし、「おまえの言ってることは嘘っぱちだ」と言った。するとスメルジャコフは、聖書に書いてある「あなたの信仰がたとえ麦粒みたいにちっぽけでも、山に向かって海へ入れと命じたら、あなたの最初の一声で山はためらわずに海に入っていくだろう」という言葉を引き合いに出し、こう言った。「グリゴーリーさん、かりにぼくが不信心者で、あなたがひっきりなしにぼくを罵倒できるくらい立派なキリスト教徒でおありなら、ためしにご自分であの山に言ってみるといいんです。(中略)そしたらすぐにおわかりになりますよ。どんなに大声を張りあげたって何ひとつ動いてくれやしない、そっくり元のままだってことがです」。
この「論争」の部分を読みながら、私は、遠藤周作の『沈黙』を思い出していた。
『沈黙』のテーマに通じるものがここにあると思った。

「背中の皮膚をもう半分ひん剥かれてるのに、自分が叫んだり喚いたりしてるのに、それでも山は動いてくれないんですよ。そんな瞬間には、もう疑いが起こるだけじゃなくて、恐ろしさのあまり分別だってなくすかもしれませんよ。そうなったら、物事の判断なんてまったく不可能です。だったら、どうしてぼくは特別に罪深いことになるんです。この世にもあの世にも利益や褒美がみつからず、せめて自分の皮膚を守ろうとすることが? ですから、ぼくはひどく神さまのお慈悲を当てにして、すっぱり許していただけるだろうっていう望みをいだいているわけなんです……」(第1巻352~353頁)
第1部、第3編、第8節「コニャックを飲みながら」

【要約】
フョードルはコニャックをぐいとあおった後、「おまえら、イエズス会士ども、さっさと下がれ」と召使たちに向かって言って、スメルジャコフとグリゴーリーを退出させた。そしてイワンに、「スメルジャコフはよっぽどおまえにご執心とみえるな、どうやってああ手なずけた?」と訊いた。イワンは何もしていないと答え、「ぼくを勝手に尊敬する気になっただけでしょう。あんなのは、ただの召使で下司にすぎませんよ。そりゃ、時代がくれば、肉弾にもなれるでしょうがね」と続けた。フョードルはアリョーシャに向かって言った。「悔しいのは、さっき院長の食事会に出られなかったことだよ。アリョーシャ、さっきはおまえんとこの院長さんをさんざん怒らせたが、どうか悪く思わんでくれ。つい意地になってしまうんだ。だって、神さまがいるなら、悪いのはむろんこのおれなんだから、責任はとる。だが、もし神さまがぜんぜんいないってことになったら、あの連中、おまえんとこのあの神父たちなんかあの程度じゃすまされなくなるんだぞ。じっさいそうなったら、首をはねられるぐらいじゃ足りない。なにしろ進歩を遅らせているのは、あの連中だからな」。そして、イワンに向かって、「イワン、答えてくれ。神さまはいるのか、いないのか」と訊いた。イワンは「いません、神なんていませんよ」と答えた。フョードルは同じ質問をアリョーシャにもしてみた。するとアリョーシャは、「神さまはいます」と答えた。フョードルは「不死」についてもイワンとアリョーシャに問い、イワンは「不死もありません」と答え、アリョーシャは「あります。神さまのなかに不死もあるのです」と答えた。フョードルはアリョーシャに、「おキツネさん」だったおまえの母親を一度だけ侮辱したことがあると言い、「聖像に唾を吐きかけも、おれの身にはなにもおこらないぞ!」と言ったら、アリョーシャの母親がヒステリーの発作を起こしたエピソードを話す。すると、その話を聞いたアリョーシャも、母親と同じヒステリー症状を起こした。その姿が、母親と異常なくらい似ていたことにフョードルは打ちのめされる。と、そのとき、玄関口からいきなり恐ろしいも物音と騒ぎ声と叫び声が響き、ドアがさっと開き、ドミートリーが広間に飛び込んできたのだった。
劇的な展開に、頁をめくる手が止まらない。
「肉弾」が意味するものとは?
「時代がくれば、肉弾にもなれる」とは、何かの伏線なのか?
ミステリー要素も含みつつ、その中に、
「神はいるのか、いないのか」
「不死はあるのか、ないのか」
という究極の問いも投げかけてくる。
実に奥深く、考えさせながら、読者を物語世界へといざなう。
ドミートリーが飛び込んできて、一体どうなるのか?
次回で、第1巻を読了する予定だ。