『カラマーゾフの兄弟』読了計画の第7回は、(これまでの記事はコチラから)
第1部、第3編「女好きな男ども」の、

第1節、第2節。
カラマーゾフの屋敷の離れに住む、グリゴーリー老人と老妻のマルファの事、
フョードルとグリゴーリーとの関係性、
また、若い下男のスメルジャコフがここにいる理由などが語られる。

第1部、第3編、第1節「下男小屋で」

【要約】
フョードル・カラマーゾフの屋敷は、かなり老朽化していたが、なかなか感じの良い外観をしていた。この物語の舞台となった当時、母屋にはフョードルと息子イワンの二人、召使用の離れには、グリゴーリー老人と老妻のマルファ、まだ若い下男のスメルジャコフの三人が住んでいるだけだった。グリゴーリーは、頑固一徹な正直者で、袖の下がきかない潔癖な男だった。フョードルは、強気なたちのくせに、人生上のいくつかの事柄では弱気になるので、誰か忠実な人間がついていなければ心細かったが、その点、グリゴーリーは申し分なく信頼できる男だった。これまでも殴られそうになったフョードルの窮地を何度も救ってくれていた。グリゴーリーとマルファの二人は、子どもを授からなかった。赤ん坊が一人いたが、その子もすぐに死んでしまった。グリゴーリーは子ども好きだったので、アデライーダが駆け落ちしたとき、3歳になるドミートリーを引き取り、1年にわたって面倒をみてやった。その後、イワンとアレクセイの面倒もみている。我が子が亡くなったその日の夜中、マルファは赤ん坊に似た泣き声を耳にした。夫はじっと耳を澄ましてから、「あれはきっとあの子が泣いて自分を呼んでいるんだ」と言いはり、庭に出た。呻き声は庭の木戸の近くに建つ風呂場から聞こえてきた。風呂場の戸を開けると、そこにはリザヴェータ・スメルジャーシチャヤというあだ名で知られ、あちこちの通りをうろついている神がかりの女がいて、たった今赤ん坊を産み落としたところだった。赤ん坊のそばで母親は死にかけていた。女は何ひとつしゃべらなかった。もともと口がきけなかったからである。
第1部、第3編、第2節「リザヴェータ・スメルジャーシチャヤ」
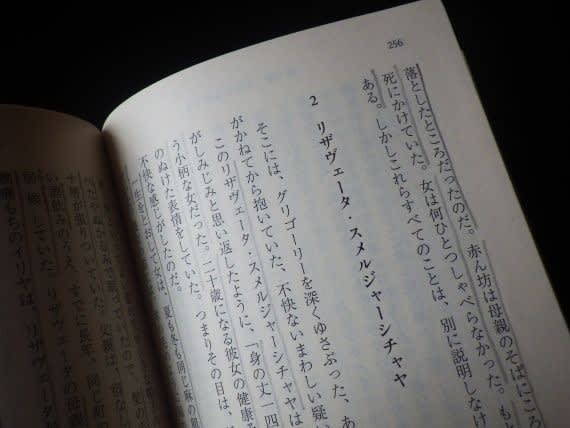
【要約】
リザヴェータ・スメルジャーシチャヤは、身の丈140cmそこそこしかない、たいそう小柄な20歳の女だった。一生を通して、夏も冬も同じ麻の肌着を身につけたまま、裸足で歩きまわっていた。いつも地べたやぬかるみで眠っていたので、髪の毛は土や泥にまみれ、落ち葉や木っ端やカンナ屑が張りついていた。父親は、宿無しの酒飲みの落ちぶれた病気がちの商人イリヤで、金持ちの商人に家に使用人のようなかたちで居候していた。リザヴェータの母親はだいぶまえに死んでいた。リザヴェータは「神がかり」だというので、町のどこにでも転がりこむことができたし、父親が死ぬと、信心深い町じゅうの人々から、孤児として愛される存在になった。小銭をもらっても、彼女はすぐに小銭を教会や刑務所へ持って行き、募金箱へ投げ入れてしまう。市場で輪っかや三日月のパンをもらっても、それを道で出会った子どもにくれてしまう。本人が口にする食事といえば、黒パンと水だけだった。あるとき(とは言っても、かなり昔の話だが)こんな出来事があった。9月の満月の夜、町の若旦那衆5、6人が遊び疲れ酔いつぶれて裏道を歩いていたところ、野菜畑でリザヴェータが眠っているを見つけた。げらげら笑いながら卑猥な冗談を浴びせていたが、一人の若旦那が、「まあ、誰でもいいが、こういうけだものを女としてまともに扱えるやつっているかね。たとえば、この場で、いま……」と言った。皆は嫌悪の色を浮かべ、「それは無理というものだ」と口々に断じる中、たまたまその仲間の一人に居合わせたフョードルが、やにわに前に飛び出して言い切った。「女として扱える、それもかなりまともに扱える、むしろ一種独特の色っぽさがあって悪くない」等々。旦那衆は思いがけないせりふを聞いて大笑いし、さっさと帰宅した。あとになってフョードルは、「あのときは自分も連中と一緒に帰った」と十字まで切って言い張ったが、事の有無は誰にも分らなかった。ところが、それから5、6ヶ月が経ち、町じゅうの誰もが、リザヴェータがお腹を大きくして歩きまわっていることに気づく。
そして、女を辱めたのはフョードルだという噂が広まる。富裕な商人の未亡人がリザヴェータを自宅に引き取り、お産がすむまでは表に出さないように指示していたが、リザヴェータは最後の日の夜にその家を抜け出し、フョードル・カラマーゾフの家に姿を現し、出産したのだった。赤ん坊は一命をとりとめたが、リザヴェータは明け方近くに息を引き取った。グリゴーリーとマルファは赤ん坊を育てることにし、フョードルもそれに異を唱えなかったが、すべてのいきさつについては躍起になって否定し続けた。それでも、フョードルはこの捨て子に姓まで考えてやった。母親のリザヴェータ・スメルジャーシチャヤにちなみ、スメルジャコフと名づけたのだ。こうしてスメルジャコフはカラマーゾフ家の二人目の下男となり、グリゴーリー夫妻と共に離れに住み、料理番として使われたのだった。
ある文献を読んでいたら、リザヴェータ・スメルジャーシチャヤとは、「いやな臭いを発するリザヴェータ」の意とあった。
スメルジャコフも、直訳すれば「臭い男」。
スメルジャコフは、神がかりの女リザヴェータ・スメルジャーシチャヤにフョードルが産ませた子だという噂はあるが、小説の中にはそれ以上のことは書かれておらず、
スメルジャコフの父親は誰なのか謎のままである。
スメルジャコフの名前は「パーヴェル」、父称は「フョードロヴィチ」、姓は「スメルジャコフ」で、父称が「フョードロヴィチ」であることは、彼の父がフョードルであることを意味している。
だが、フョードルは、スメルジャコフを自宅に置いて、自分の父称まで分け与えておきながら、なぜカラマーゾフの姓を名乗らせなかったのか?
文献には、「血縁関係」の否定とあった。
第1部、第3編のタイトルに「女好きな男ども」とあるように、
カラマーゾフ家の人間は「女好きな男ども」であり、
それはアリョーシャも例外ではない。(彼も徐々に性に目覚めていくとのこと)
カラマーゾフとは、いわば「性」そのものなのだ。
そういったカラマーゾフの血縁関係を否定するものとして、
カラマーゾフ家から切り離されたものとして、
スメルジャコフは存在するのだ。
文献には、スメルジャコフは「女嫌い」とあり、
このスメルジャコフが「この物語の影の主人公ともいえる存在」との記述もあった。
今後のスメルジャコフの動向にも目が離せない。
