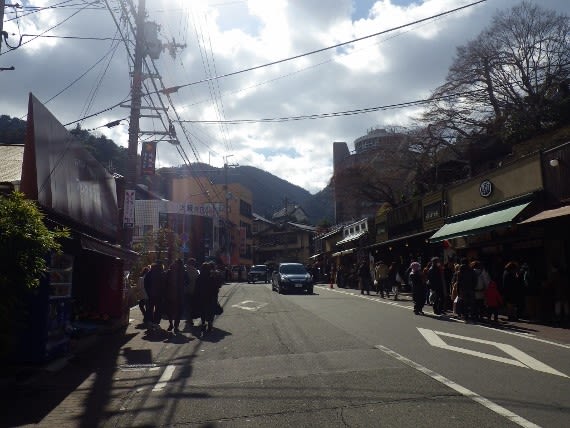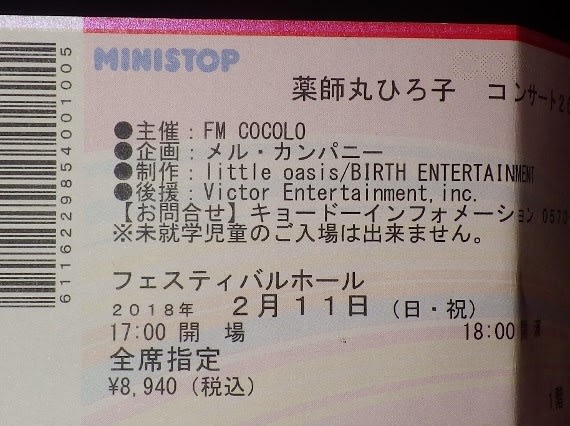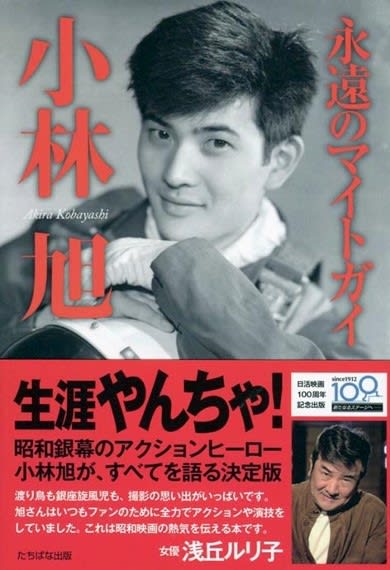吉田大八監督作品である。

これまで、
『腑抜けども、悲しみの愛を見せろ』(2007年)
『クヒオ大佐』(2009年)
『パーマネント野ばら』(2010年)
『桐島、部活やめるってよ』(2012年)
『紙の月』(2014年)
『美しい星』(2017年)
など、数は少ないけれど、
優れた作品を創り続けている監督である。
吉田大八監督の新作が公開されたなら、
映画ファンならば、
まずはさておいても見ておかなければならないだろう。
この『羊の木』には、
私の好きな松田龍平、田中泯、木村文乃、市川実日子、優香、安藤玉恵なども出演している。
寒波が襲来した日の夜、
(そんな日は観客は少ないだろうと)
会社の帰りにワクワクしながら映画館へ向かったのだった。

寂れた港町・魚深(うおぶか)に、
それぞれ移住して来た6人の男女。
福元宏喜(水澤紳吾)
太田理江子(優香)
栗本清美(市川実日子)
大野克美(田中泯)
杉山勝志(北村一輝)
宮腰一郎(松田龍平)

彼らの受け入れを担当することになった市役所職員・月末一(錦戸亮)は、
この6人の移住が、国の極秘プロジェクトであることを知る。
過疎問題を解決するために、町が身元引受人となって、元受刑者を受け入れたというのだ。
月末や町の住人、そして6人にもそれぞれの経歴は明かされなかったが、
やがて月末は、6人全員が元殺人犯だという事実を知ってしまう。

理髪店に勤務する福元宏喜(水澤紳吾)
殺人(懲役7年)

介護センターに勤務する太田理江子(優香)
殺人(懲役7年)

清掃員として勤務する栗本清美(市川実日子)
殺人(懲役6年)

クリーニング店に勤務する大野克美(田中泯)
殺人(懲役18年)

釣り船屋に勤務する杉山勝志(北村一輝)
傷害致死(懲役8年)

宅配業者として勤務する宮腰一郎(松田龍平)
傷害致死(懲役1年6ヶ月)

月末が高校時代に思いを寄せていた石田文(木村文乃)が帰郷してきて、

受刑者の一人、宮脇と付き合い出したことにより、

月末の心にも、魚深の町にも、
不穏な空気が漂い始める。
そして、港で起きた死亡事故をきっかけに、
殺人歴がある犯罪者と、
かれらを受け入れた町の住民との間に、
少しずつ狂いが生じていく……

山上たつひこといがらしみきおによる、
第18回文化庁メディア芸術祭優秀賞(マンガ部門)に輝いた問題作を、
アレンジを加え、吉田大八監督が実写映画化したもので、
移住した6人の(殺人歴のある)元受刑者のキャラが立っており、
平凡な魚深市役所職員・月末との対比が絶妙で、
2時間6分、面白く見ることができた。
この映画は、
最初から最後まで、不穏な空気に覆われている。
仮釈放された殺人犯が6人もやってくるのだ。
それを知っているのは、市役所の一部の人間だけで、
町の住民は知らない。
だが、6人の醸し出す雰囲気は尋常ではない。
次第に嫌な空気が漂いはじめ、
町民の間にもじわじわと不穏さが染みわたっていく。
6人の受け入れを担当させられた月末も、事あるごとに、
「信じるか?」「疑うか?」
の局面に立たされる。

考えてみるに、
ただ知らないだけで、
元犯罪者は、私たちの住む町に、当然のことながらいるだろうし、
日々、日常に溶け込んで生活しているに違いない。
その人の過去を知ってしまったとき、どういう行動をするのか?
映画を見ている我々も、いつ月末と同じ局面に立たされるか分らないのだ。
映画の中の物語としてだけでなく、
これから起こりうる問題として、
観客はちょっとドキドキしながらこの映画を見ることになる。
私は、原作は未読であるが、
この『羊の木』の舞台は、寂れた港町という設定で、
閉じられた世界の中の、きわめて文学的な、ある種のユートピアではないかと考えた。
とても魅力的な空間だったからだ。
世間から隔絶し、閉じている世界は、
その内側がいかに過酷であろうとも、とても甘美な空間だ。
太宰治は、『パンドラの匣』の人里離れた健康道場で、
坂口安吾は、『黒谷村』などで田舎の村を舞台に、
田中英光は、『オリンポスの果実』で船の中を舞台に、
ウィリアム・ゴールディングは『蠅の王』で南海の孤島で、
イエールジ・コジンスキーは『異端の鳥』で異国の村々で、
大江健三郎は『芽むしり仔撃ち』で山奥の村で、
文学的ユートピアを構築した。
『羊の木』もまた、寂れた港町で、ユートピアを創り上げたと言える。
いや、『羊の木』の場合は、甘美なる“ディストピア”と表現すべきかもしれないが……
宅配業者として勤務する宮腰一郎を演じた松田龍平。

その存在感からして不穏で、(笑)
だからこそ、これまで、様々な役で我々を驚かせてくれた。
昨年も『散歩する侵略者』((2017年9月9日公開)での演技は素晴らしかったし、
本作でも、不気味さではピカイチであった。
市役所職員・月末一を演じた錦戸亮が“表”の主役とすれば、
“裏”の主役は、間違いなく松田龍平であろう。
映画の中盤から終盤にかけては、まさに独壇場であった。

介護センターに勤務する太田理江子を演じた優香。

「吉田大八監督、俺の優香に何させるんだ!」
と思わず叫びたくなるほど、本作での優香はエロかった。(コラコラ)
(北見敏之さん、役得です!)

優香本人は、
「普段、セクシーさとかけはなれているので、エロかったね~って言われるととってもうれしいです」
と語っていたが、
30代後半となった彼女の、
役の幅を広げることのできた今回の太田理江子役であったと思う。
今後の活躍が益々楽しみになってきた。

クリーニング店に勤務する大野克美を演じた田中泯。

元ヤクザの役ということで、
その目の鋭さは超一級であった。
言葉は発さなくても、その存在感で相手を圧倒する。
だが、雇人であるクリーニング店主・内藤朝子(安藤玉恵)の前では、
優しい表情を見せる。
私の好きな安藤玉恵も、ここで実に好い演技をしている。

釣り船屋に勤務する杉山勝志を演じた北村一輝。

見るからに悪いことをしそうな顔をしているが、(褒めています)
本作でも、物語の発火点の役割を果たしている。
彼がいなかったら、『羊の木』という物語は動き出さないし、
彼がいたことで、この映画は面白くなっている。
先日見た『8年越しの花嫁 奇跡の実話』とは真逆の役柄だが、
話題作に立て続けに出演しているということは、
多くの監督に愛されているからであろう。
すぐに公開が始まる、
『今夜、ロマンス劇場で』(2018年2月10日公開)
『去年の冬、きみと別れ』(2018年3月10日公開)
にも出演しているので、こちらも楽しみ。

理髪店に勤務する福元宏喜を演じた水澤紳吾。

『SR サイタマノラッパー』など、
入江悠監督作品の常連俳優という印象であるが、
最近では、
李相日監督作品『怒り』(2016年)や、
三島有紀子監督作品『幼な子われらに生まれ』(2017年)などにも出演しており、
いろんな作品でよく目にするようになってきた。
本作でも重要な役を得ての出演で、
地味ながらドキッとさせる演技で、観客を魅了した。
特に、酒を呑んで暴れるシーン、月末の髭剃りをするシーンは秀逸で、
(良い意味で)ヒヤヒヤ、ハラハラさせられた。

清掃員として勤務する栗本清美を演じた市川実日子。

一昨年(2016年)あたりから映画出演が急に増えて、
『ミュージアム』(2016年)
『シン・ゴジラ』(2016年)
『夜空はいつでも最高密度の青色だ』(2017年)
『三度目の殺人』(2017年)
『ナラタージュ』(2017年)
『DESTINY 鎌倉ものがたり』(2017年)
など、傑作、話題作でよく見かけるようになった。
しかも、印象に残る演技で、
一度見ると、忘れられなくなる。
本作『羊の木』では、セリフがほとんど無く、
表情や動きだけで表現するシーンが多かったが、
『羊の木』というタイトルに関わる重要な役であったが、
その役目を十分に果たしていた。

清掃員の栗本清美が、
浜辺の清掃をしているとき、
浜辺に流れ着いた缶のフタを拾う。
そのフタには、羊の木が描かれていた。

【羊の木】とは、
西洋につたわる伝説の植物で、
「東タタール旅行記」には、次のように記されているという。
その種子やがて芽吹き タタールの子羊となる
羊にして植物
その血 蜜のように甘く
その肉 魚のように柔らかく
狼のみ それを貪る
中世の時代、西欧では、
「東方には羊のなる木がある」
と信じられていたという。
当時、西欧では「木綿」の存在が知られておらず、
交易でもたらされる「綿花」を見て、
「羊の木」の存在を想像したようだ。
羊の毛は、刈っても、また生えてくる。
何度刈っても、また生えてくる。
だから、「羊の木」は“再生”を意味しているのかもしれない。
究極の犯罪・殺人を犯した者が、
はたして一般社会で“再び”普通に生活できるのか?
栗本清美は、浜辺で拾った「羊の木」が描かれた缶のフタを持ち帰り、
アパートの戸に掛ける。
栗本清美はいろんな生き物の死骸を土に埋め、
その上に土饅頭を作っている。
その盛られた土饅頭から、ラスト、植物の芽が顔を出す。
それが、“再生”の象徴のようで、ちょっと救われた。
衝撃的なシーンも多いが、
ラストには希望がほの見えた作品であった。

エンドロールに流れる主題歌は、
ボブ・ディランの楽曲をオーストラリアの鬼才ニック・ケイブがカバーした、
「DEATH IS NOT THE END」
これがまたシブい。
映画館で、ぜひぜひ。