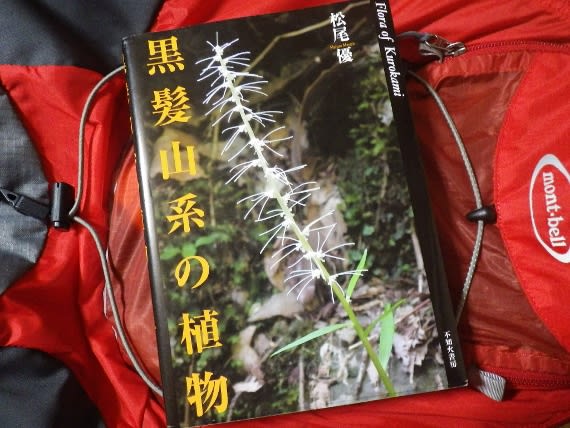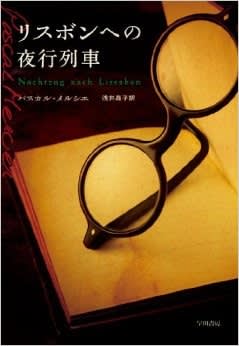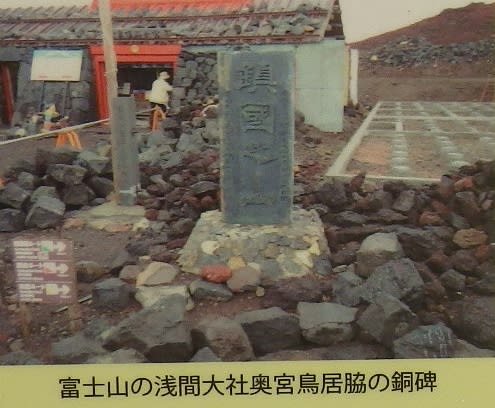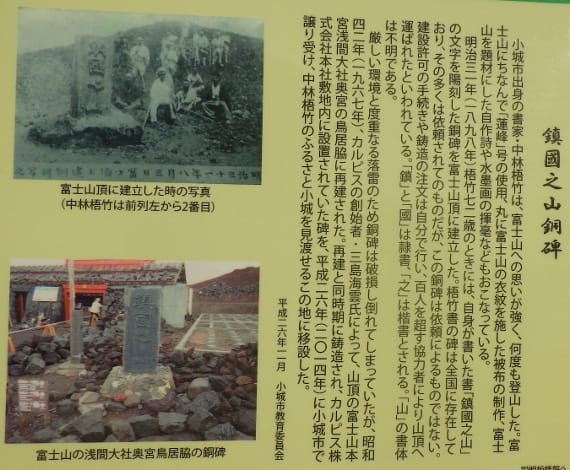ヤスさんから、
「10月1日(水)は午後から仕事ですが、午前中にぜひ山に登りたいです」
とのメールが届いた。
さて、どこの山にしようか……
思案した結果、
ダンギクの咲く登吾留山に決めた。
(ダンギクはクマツヅラ科の多年草で、日本の九州西部、朝鮮西部から中国、台湾の暖温帯や亜熱帯に分布する)
ついでに、ナメラダイモンジソウも愛でてくることにしよう。
登吾留山まではそう時間もかからないし、
朝早く出発すれば、
正午までには余裕で戻って来られるだろう。
ヤスさんと某所で待ち合わせをし、
一路、登吾留山へ。
登山口に着き、準備をし、軽くストレッチ。
ゆっくりスタートする。
雰囲気の良い登山道を登って行く。
![]()
一汗かいた頃に、岩場に出る。
![]()
カラスノゴマや、
![]()
ホソバヤマジソや、
![]()
コシオガマが出迎えてくれる。
![]()
ヤマラッキョウも多いが、
![]()
開花にはもう少し時間がかかりそう。
![]()
ダンギクはどうだったかというと……咲いてました〜
それも、たくさん。
![]()
美しい〜
![]()
あっちにも、こっちにも……
![]()
二段、
![]()
三段、
![]()
四段……
下の段から開花してくるんだね。
![]()
花も美しいけれど、
蕾も得も言われぬ美しさ。
![]()
上から見ると、宝石のよう。
![]()
ひとつの蕾が開き始める。
![]()
やがて、次々と開花する。
![]()
そして、全開となる。
![]()
ダンギクは、花だけではなく、葉も美しい。
葉を上から見ても美しいが、
![]()
横から見ると、より一層美しい。
![]()
ねっ。
![]()
もちろん、花も……
![]()
極上の一輪を求めて彷徨う。
![]()
![]()
この花も美しいが、
![]()
あの花も美しい。
![]()
ひとり寂しく咲いている花に心惹かれるし、
![]()
岩場に立つ花にも魅せられる。
![]()
ヤスさんも、激写につぐ激写。
![]()
大満足のダンギク観賞登山であった。
![]()
さて、次は、ナメラダイモンジソウの群生地へ向かうことにしよう。
途中には、サクラタデの群生地が……
![]()
美しい。
![]()
![]()
美し過ぎる。
![]()
見上げると、白い花が見えた。
![]()
ナツツバキのようにも見えるが、
ナツツバキの花期は6月〜7月。
花に詳しい山友に問い合わせると、
「サザンカの原種ではないかしら?」
とのこと。
![]()
沢へ下りて行く。
![]()
ナメラダイモンジソウはというと……咲いてました〜
![]()
少し来るのが早かったかな〜と思ったが、
思いのほかたくさん咲いていた。
![]()
ヤスさんも大感激。
![]()
「本当に大の字ですね〜」
と妙に感心している。(笑)
![]()
ここでも激写につぐ激写。
![]()
今日も「一日の王」になれました〜![]()
![]()
![]()
「10月1日(水)は午後から仕事ですが、午前中にぜひ山に登りたいです」
とのメールが届いた。
さて、どこの山にしようか……
思案した結果、
ダンギクの咲く登吾留山に決めた。
(ダンギクはクマツヅラ科の多年草で、日本の九州西部、朝鮮西部から中国、台湾の暖温帯や亜熱帯に分布する)
ついでに、ナメラダイモンジソウも愛でてくることにしよう。
登吾留山まではそう時間もかからないし、
朝早く出発すれば、
正午までには余裕で戻って来られるだろう。
ヤスさんと某所で待ち合わせをし、
一路、登吾留山へ。
登山口に着き、準備をし、軽くストレッチ。
ゆっくりスタートする。
雰囲気の良い登山道を登って行く。

一汗かいた頃に、岩場に出る。

カラスノゴマや、

ホソバヤマジソや、

コシオガマが出迎えてくれる。

ヤマラッキョウも多いが、

開花にはもう少し時間がかかりそう。

ダンギクはどうだったかというと……咲いてました〜
それも、たくさん。

美しい〜

あっちにも、こっちにも……

二段、

三段、

四段……
下の段から開花してくるんだね。

花も美しいけれど、
蕾も得も言われぬ美しさ。

上から見ると、宝石のよう。

ひとつの蕾が開き始める。

やがて、次々と開花する。

そして、全開となる。

ダンギクは、花だけではなく、葉も美しい。
葉を上から見ても美しいが、

横から見ると、より一層美しい。

ねっ。

もちろん、花も……

極上の一輪を求めて彷徨う。


この花も美しいが、

あの花も美しい。

ひとり寂しく咲いている花に心惹かれるし、

岩場に立つ花にも魅せられる。

ヤスさんも、激写につぐ激写。

大満足のダンギク観賞登山であった。

さて、次は、ナメラダイモンジソウの群生地へ向かうことにしよう。
途中には、サクラタデの群生地が……

美しい。


美し過ぎる。

見上げると、白い花が見えた。

ナツツバキのようにも見えるが、
ナツツバキの花期は6月〜7月。
花に詳しい山友に問い合わせると、
「サザンカの原種ではないかしら?」
とのこと。

沢へ下りて行く。

ナメラダイモンジソウはというと……咲いてました〜

少し来るのが早かったかな〜と思ったが、
思いのほかたくさん咲いていた。

ヤスさんも大感激。

「本当に大の字ですね〜」
と妙に感心している。(笑)

ここでも激写につぐ激写。

今日も「一日の王」になれました〜















































































 )
)